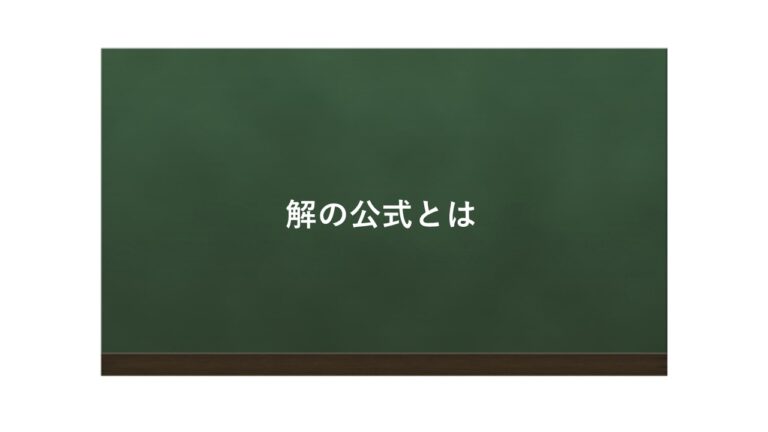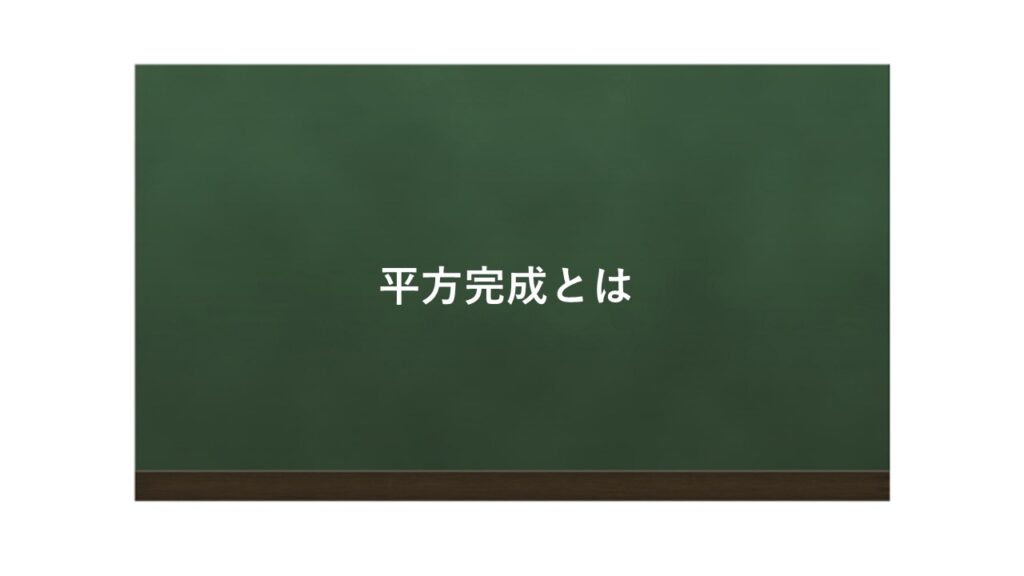実は二次方程式を解くには1つ、超便利なアイテムがあります。
それは解の公式というもの。
解の公式を使えば二次方程式は必ず解けます。
ただはっきり言って複雑。あまりの複雑さゆえになかなか覚えられず、
二次方程式の解の公式をわかりやすく教えて
と検索してこのページに来た人も多いと思います。
解の公式とは
解の公式に当てはめればどんな二次方程式も必ず解けます。
それはつまり、わざわざ平方完成しなくても少しだけ簡単に二次方程式を解けるということ。
ということでまずは解の公式を暗記しましょう。
解の公式
二次方程式 $ax^2+bx+c=0\quad(a\neq0)$ の解は
$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
で求められる
分数で文字があってルートもあれば2乗もある、初見には強烈な公式です。
暗記しろといわれてもそうそう簡単に暗記できそうにありません。
思わず
「二次方程式の解の公式をわかりやすく教えて」
と検索してしまいますよね?
でも暗記です。
ではどうやって暗記するのか?
練習するしかありません。基本例題で練習しましょう。
ちなみに$a=0$では二次の項の係数が$0$、つまり二次の項がないことになり$bx+c=0$の一次方程式となってしまいます。
一次方程式じゃないことをはっきりさせるために$a\neq0$と示しています。
基本例題1
二次方程式$\:3x^2+5x+2=0\:$を解の公式を使って解け。
考え方
$a=3,b=+5,c=+2$として
解の公式$\:x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\:$に当てはめます。
解答
$3x^2+5x+2=0$
$\begin{align}x=&\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\\\\=&\dfrac{-(+5)\pm\sqrt{(+5)^2-4\times(+3)\times(+2)}}{2\times(+3)}\\\\=&\dfrac{-5\pm\sqrt{25-24}}{6}\\\\=&\dfrac{-5\pm1}{6}\\\\x=&\dfrac{-5-1}{6}=-1\\\\x=&\dfrac{-5+1}{6}=-\dfrac{2}{3}\end{align}$
補足
解の公式に当てはめれば、あとは計算ミスに気をつけるだけです。
$-4ac$部分で、$a$や$c$が負の値のときに計算ミスが多発するようです。
文字に数値を代入するときはしっかり(かっこ)をつけるようにしましょう。
類題を使ってさらに練習しましょう。
類題
次の二次方程式を解の公式を使って解け。
$\begin{align}(1)&\:x^2+7x+2=0\quad(2)\:2x^2+4x-3=0\\\\(3)&\:-x^2-6x+3=0\end{align}$
解答はこのページの下段にあります。
二次方程式の解き方がいろいろ出てきましたね。
いろいろあるとどの方法で解けば良いかわからなくなってきます。
二次方程式はどの方法で解けば良いか
ここまで二次方程式の解き方として、
- $x^2=〇$を解くもの
- $X^2=〇$の形に置き換えて解くもの
- $(x+a)(x+b)=0$の形に因数分解して解くもの
- 平方完成して強引に$X^2=〇$の形にして解くもの
を紹介しました。
特に、$X^2=〇$の形にできず因数分解もできないものは平方完成して、強引に二乗の形を作り出して解くということでした。
これらの方法を知っていれば二次方程式は解けます。
でも平方完成は解き終えるまでに、かなりの時間と労力を使うはずです。
ここで一度頭の中を整理しましょう。
二次方程式を解く手順
- $x^2=〇$の形もしくはこの形に変形できるなら変形して解く
- 置き換えて$X^2=〇$の形になるなら置き換えて解く
- 上記の形ができないなら因数分解して解く
- それでもうまくいかなかったら解の公式で解く
- どの方法で解くか考えるのが面倒なら最初から解の公式で解く
1がダメなら2、2がダメなら3、3がダメなら4の順で解き方の方針を決めていくと良いしょう。
解の公式は万能公式なのでぶっちゃけた話、最初から四の五の言わず解の公式で解くのもOKです。
ただ$x^2=〇$の形や因数分解ができるならそちらで解いた方がラクなことはラクです。
例えば二次方程式
$x^2=49$ は、一瞬で$x=\pm7$とわかりますよね。
いちいち解の公式を使っていたら逆に時間がかかって難しくなってしまいます。
ちなみに解の公式を使うなら
$x^2-49=0$ としてから$a=1,b=0,c=-49$なので
$\begin{align}x=&\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\\\\=&\dfrac{-0\pm\sqrt{0^2-4\times(+1)\times(-49)}}{2\times(+1)}\\\\=&\dfrac{0\pm\sqrt{0+196}}{2}\\\\=&\dfrac{\pm14}{2}\\\\x=&\pm7\end{align}$
となります。解が出る前にため息が出ます。やってられません。
なお式の展開や因数分解を自在にこなせると、どの方法で二次方程式を解けばよいか半ば反射的に思い浮かぶようになります。
「はぁ、反射的に思い浮かぶだと? 嘘だろ! そんなことあるわけない!!」と疑っているそこの君!!
嘘だと思うなら式の展開や因数分解を再度練習してみてください。
嘘じゃないことを君自身が証明することになります。
二次の項に係数があるときの二次方程式
二次の項に係数があっても$X^2=〇$の形にできるものもあれば、因数分解できるものもあります。
ただ正直なところ、二次の項に係数があると因数分解が難しくなります。
二次の項に係数があるときは解の公式を使った方が効率よく解けることが多いようです。
ところで次の二次方程式はどう解きますか?
しばらく考えてみてください。
基本例題2
二次方程式$\:3x^2+24x+45=0\:$を解け。
考え方
ここまでのことを読むと、解の公式を使おう!! となると思います。
もちろんそれでも良いですが、$3$が共通因数であることに気づければ、解の公式を使うことなく簡単に解が求まります。
解答
$\begin{align}\:3x^2+24x+45=0\\\\3(x^2+8x+15)=0\\\\x^2+8x+15=0\\\\(x+3)(x+5)=0\\\\x=-3\:,\:-5\end{align}$
解説
二次の項に係数がありましたが、共通因数の$3$でくくったことで因数分解できました。
しかも解の公式を使うよりもずっと簡単に解けました。
このように共通因数でくくることで解の公式を使わずに解けるものもあります。
「二次の項に係数があるから解の公式を使う」と考えるのは間違いないのですが、その前に、共通因数でくくり因数分解できないかを考えるようにしましょう。
二次方程式の解の公式をわかりやすく教えます
そもそもどうして解の公式が導けるのか?
二次方程式の解の公式は、平方完成をもとに導くことができます。
ざっくり言えば
$ax^2+bx+c=0$の形から$x=〇$の形
にするための強引な式変形。
ここでは$x=〇$の形を導くための式変形を1つ1つていねい(過ぎるくらい)に解説します。
平方完成なので、基本式となる
$X^2+2AX+A^2=(X+A)^2$
に照らして強引に変形します。そこから
「$x$1乗の形」を作るのが第一の目標。
そして本来の目標である
$x=$数値 の形へ持っていきます。
なお平方完成に慣れていない人は平方完成のページを確認してください。
$ax^2+bx+c=0$
$X^2+2AX+A^2$から$(X+A)^2$の形にする。
・$x^2$の係数$a$が邪魔
・$x$の係数に$2$がない
ため工夫が必要。
$a(x^2+\dfrac{b}{a}x)+c=0$
$x^2$の係数$a$が邪魔なので(かっこ)でくくる。
$a\{$$x+\dfrac{b}{a}x+(\dfrac{b}{2a})^2$$-(\dfrac{b}{2a})^2\}+c=0$
$X^2+2AX+A^2$$=(X+A)^2$
$\dfrac{b}{a}$が$2A$に相当。
そのため
$\dfrac{b}{2a}$が$A$に相当。
$a\{$$(x+\dfrac{b}{2a})^2$$-\dfrac{b^2}{4a^2}\}+c=0$
$(x+\dfrac{b}{2a})^2$が$(X+A)^2$に相当。
$x$1乗の形を作れた。
第一目標完了。
ここまでが第一目標。
3~4行目の式が最大の難所なので、そこをしっかり確認してください。
あとは$a$の扱いに注意しながら式変形を続けます。
$a(x+\dfrac{b}{2a})^2-\dfrac{b^2}{4a}+\dfrac{4ac}{4a}=0$
あとは$x=$の形を作るために等式の変形。
$a(x+\dfrac{b}{2a})^2=\dfrac{b^2}{4a}-\dfrac{4ac}{4a}$
左辺の(かっこ)の外にある$a$で両辺割る。
$(x+\dfrac{b}{2a})^2=\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$
左辺(かっこ)の中を割らないように注意。
$(x+\dfrac{b}{2a})=\pm\sqrt{\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}}$
$x=$の形を作るので1乗にする。
右辺は$\pm$をつけて全体に$\sqrt{\quad}$
$x=-\dfrac{b}{2a}\pm\sqrt{\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}}$
$x=-\dfrac{b}{2a}\pm\dfrac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
完成
もっとコンパクトにまとめることもできますが、1つ1つの変形をじっくり書くことを目的にしていたので超longになってしまいました。
解の公式はまずは暗記。
暗記ができて二次方程式の解法に余裕が出てきたら、解の公式の求め方を理解してください。
類題 解答
$\begin{align}(1)&\:x^2+7x+2=0\\\\x&=\dfrac{-(+7)\pm\sqrt{(+7)^2-4\times1\times(+2)}}{2\times1}\\\\&=\dfrac{-7\pm\sqrt{49-8}}{2}\\\\&=\dfrac{-7\pm\sqrt{41}}{2}\\\\x&=\dfrac{-7\pm\sqrt{41}}{2}\end{align}$
$\begin{align}(2)&\:2x^2+4x-3=0\\\\x&=\dfrac{-(+4)\pm\sqrt{(+4)^2-4\times(+2)\times(-3)}}{2\times2}\\\\&=\dfrac{-4\pm\sqrt{16+24}}{4}\\\\&=\dfrac{-4\pm\sqrt{40}}{4}\\\\&=\dfrac{-4\pm2\sqrt{10}}{4}\\\\x&=\dfrac{-2\pm\sqrt{10}}{2}\end{align}$
$\begin{align}(3)&\:-x^2-6x+3=0\\\\ x&=\dfrac{-(-6)\pm\sqrt{(-6)^2-4\times(-1)\times(+3)}}{2\times(-1)}\\\\&=\dfrac{6\pm\sqrt{36+12}}{-2}\\\\&=\dfrac{6\pm\sqrt{48}}{-2}\\\\&=\dfrac{6\pm4\sqrt3}{-2}\\\\&=-\dfrac{6\pm4\sqrt3}{2}\\\\&=-3\pm2\sqrt3\end{align}$
補足
$-x^2-6x+3=0$のように二次の項の係数が負のときは、先に両辺を$-1$倍して$x^2+6x-3=0$と二次の項の係数を正にしてから計算してもかまいません。
ただそのときは全ての項の符号が逆になるので気をつけましょう。
$\begin{align}&x^2+6x-3=0\\\\x&=\dfrac{-(+6)\pm\sqrt{(+6)^2-4\times(+1)\times(-3)}}{2\times1}\\\\&=\dfrac{-6\pm\sqrt{36+12}}{2}\\\\&=-3\pm2\sqrt3\end{align}$